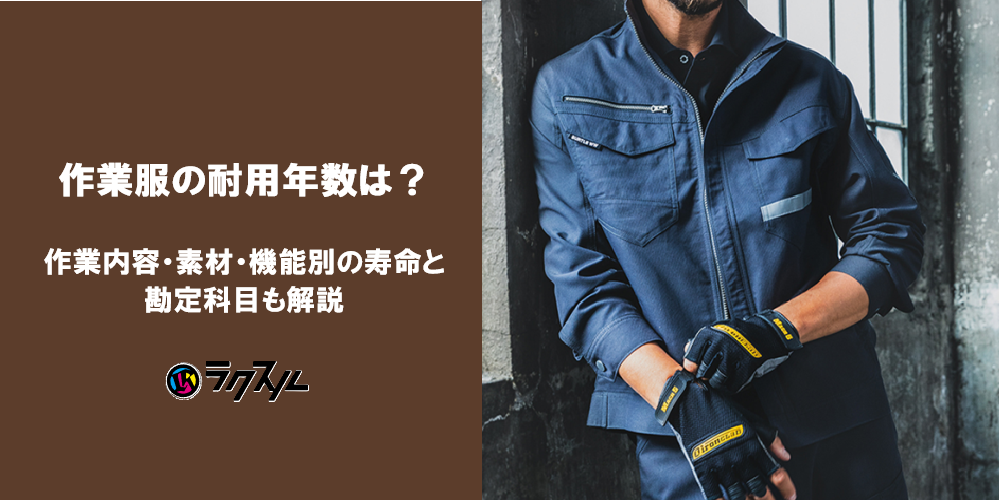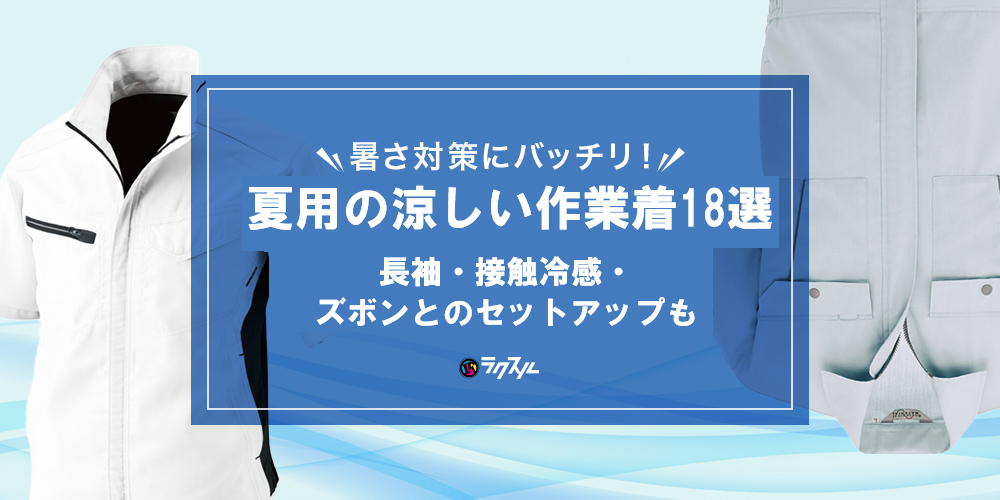作業服は頑丈なつくりのものが多いため、長持ちするイメージがあるかもしれません。しかし、実際の耐用年数は3年以内が目安です。また、環境・条件によって大きく左右されます。
そこで本記事では、作業服の耐用年数を仕事内容と環境、ウェアの素材、機能、行政の被服規程などの観点から詳しく解説します。後半では、ウェアの寿命を縮めるNG行動や経理上の法定耐用年数も解説するので、ぜひ参考にしてください。
作業着の耐用年数は職種・環境で異なる
まずは職種・環境別のウェアの耐用年数の目安を解説します。
デスクワーク中心なら3年が目安
デスクワークが中心なら、熱・日光・汗・摩耗などによる劣化が少ないため3年程度は快適に着用できます。ただし、定期的な洗濯が前提です。
また、背中やボトムスは早めに劣化する可能性もあるので、定期点検をおこないましょう。椅子と接地する部分は摩擦が起こりやすく、スレや毛羽立ち、テカりが気になることがあります。
建設業・工場などでは1~3年が目安
建設業・工場で使う作業服の耐用年数は1~3年が目安です。次の要素によってウェアの寿命が縮む傾向にあります。
-
汗
-
粉塵
-
摩擦
-
ひっかけ
-
機械油
-
洗剤(機械洗浄等)
-
紫外線(屋外作業)
汗や粉塵が繊維の隙間に入り込み、洗濯しても落とせない微粒子が蓄積すると、通気性や撥水などの各種機能が低下します。一見するときれいに洗濯できていても、快適性に劣化を感じるでしょう。
また、建設業や工場では体を大きく動かすシーンや、狭い場所での作業も多いため、生地同士が擦れやすく摩耗による劣化が生じやすいといえます。生地が薄くなってきたら、穴が開く可能性が高いため買い換え時です。機材を使用する際のひっかけにも注意しましょう。
機械油や洗剤の付着は、色褪せや機能低下を引き起こすことがあります。これらを落とすために強力な洗剤を使って洗濯することも、生地の寿命を縮める要因です。
紫外線も生地や機能を劣化させます。とくに綿製のウェアは紫外線による変色や変質が起こりやすいため注意が必要です。
鉄工所などハードな環境下では1年未満
火のそばや高温下で作業する、鉄工所をはじめとした業務では作業服が早く劣化する傾向にあります。熱や火の粉が生地にダメージを与えるからです。
火気を扱う現場で作業服に穴が開いていると、火の粉の侵入によってインナーに引火する恐れがあります。事故を防ぐためにも、使用のたびに穴の有無や生地の劣化具合を確認し、不具合があれば交換しましょう。
また、目に見える問題がない場合でも、通気性や加工による機能などが低下している可能性があります。安全と快適性を保つために、6カ月~1年を目安に交換することをおすすめします。
素材別の耐用年数
生地に使われている素材によっても耐用年数は変化します。ここでは、作業服に使われることの多い綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンの耐用年数の目安を紹介します。
綿は3~5年
綿(コットン)100%の生地の耐用年数は3~5年が目安です。
耐熱性があり、高温にさらされても溶けて穴が開く心配がありません。200度弱の温度に数分間晒すと変色、230度前後で分解・炭化が始まり、280度以上で燃焼するという程度です。発火点は366度とされています。
また、アルカリ性の洗剤に強いという特徴もあります。膨潤(マーセル化)して繊維同士に隙間ができることはあっても、損傷はしません。
デメリットは、しわがつきやすいことと、長時間直射日光に晒すと黄ばみ(黄変)が生じやすいことです。また、水分を含みやすいため、カビにも注意しましょう。
ポリエステルは4~5年
ポリエステル100%の生地の耐用年数は4~5年が目安です。
アルカリ性洗剤や溶剤に強く、耐薬品性が重視されるウェアで採用される傾向にあります。また、紫外線に晒しても強度はほとんど変わりません。また、虫やカビにも強いというメリットがあります。しわもつきにくいので、きれいな見た目を保ちやすい素材です。
一方、熱には弱いため高温下での作業には向きません。240度前後で変質が始まり、250度を超えると溶ける恐れがあります。溶けたポリエステルが肌に付着すると、やけどが重症化しやすいため注意しましょう。
ナイロンは4~5年
ナイロン100%の生地の耐用年数は4~5年が目安です。
耐摩擦性に優れた素材で、耐久性の高さからアウトドア用品で広く使われています。また、耐薬品性に優れているのも特徴です。アルカリ・酸に対して一定程度の強さをもち、他の化学薬品に対しても抵抗性があるほか、一般溶剤では溶解しません。
ただし、200度程度の高温に晒されると溶ける可能性があります。また、紫外線によって強度が下がり、黄変することもあります。丈夫に見えても4~5年を目安に交換しましょう。
ポリウレタンは3年
ポリウレタンはストレッチ・弾力性の追加、防水加工などで使われる素材です。ポリウレタン100%はゴムに似ているため、作業服で使われるときは他の素材と混紡されます。ポリウレタン単体の寿命は3年程度です。
強酸や強アルカリの影響はほとんどなく、一般溶剤でもほとんど変化しません。虫やカビにも強いため、清掃や器具洗浄などで役立つでしょう。
ただし、紫外線や塩素系漂白剤の使用には弱く、強さが低下したり、黄変したりします。また、ポリウレタンコーティングによる防水加工は加水分解で劣化しやすいため、湿気の多い場所で保管するのは避けましょう。作業服の寿命を縮める要因となります。
機能別の耐用年数
生地の耐用年数以内であっても、付加機能の効果の寿命が短いことがあります。ここでは、撥水・防水機能とUVカット機能の耐用年数の目安を紹介します。
撥水・防水は1年~5年
撥水・防水加工のウェアの耐用年数は1~5年と幅があります。雨天時のみの着用であれば5年ほどは撥水・防水効果が続く傾向にありますが、清掃等で毎日使用する場合は1年未満の場合もあります。
ただし、いずれの場合も適切に管理した場合の年数です。撥水・防水コーティング仕様の場合、洗濯や使用時の摩擦によってコーティングが剥がれやすくなります。洗濯ネットに入れる(※)、手洗いするなど摩擦を低減する工夫をおこないましょう。
また、ポリウレタンコーティングの場合は日光や湿気に弱いため、洗濯後は日陰かつ通気性の良いところに干し、しっかり乾いてから取り込みましょう。
(※)防水ウェアは、洗濯機で洗うと洗濯機が故障する恐れがあるため、手洗いが推奨されています。
ゴアテックスは例外
ゴアテックスはレインウェアやアウトドア用品によく使われる防水素材です。アメリカのWLゴア&アソシエイツ社の登録商標で、ウェアでは透湿防水と防風性を備えたゴアテックスメンブレンが使われます。
ゴアテックスには経年変化がほとんどなく、寿命という概念がありません。適切に管理していれば、10年以上使用できます。
UVカットはワンシーズン~3年
UVカット加工はワンシーズン、UVカット素材は3年が耐用年数の目安です。
UVカット加工は繊維の表面にコーティングを施したもので、日々の洗濯や着用による摩擦で劣化します。来年もUVカット効果を発揮するほどの耐久性ではないので、ワンシーズンで交換しましょう。
UVカット素材は、酸化チタンや特殊セラミックなどのUVカット効果がある成分を練り込んだ繊維です。コーティングとは違って水濡れや摩擦に強いため、3年程度はUVカット効果を期待できます。ただし、価格はUVカット加工よりも高額です。
行政の被服規程・規則を参考にする
被服規程は、職員に貸与するウェアの品目・規格・貸与期間などを規定したものです。貸与期間の項目は企業が従業員に制服を貸与するときの参考になります。
消防職員被服等貸与規程
冬服は10月1日~翌年5月末日、夏服は6月1日~9月末日を着用期間として、貸与期間を定めています。貸与期間中、職員には制服の善良かつ清潔な管理が求められます。
この規程を参考にする場合、日勤者の貸与期間が目安となります。厚手で丈夫な冬服は3年、薄手の夏服は2年を目安に交換を検討しましょう。
※日勤者:平日勤務、土日休みの勤務体制の人。消防職員には24時間勤務と1日休みをおこなう交替勤務者が8割、日勤者は2割。
熊本県湯前町の被服等貸与規程
熊本県湯沢町では、建設水道課や農林振興課の作業服、および保健福祉課環境衛生係の予防衣、保育所職員の保育服などの貸与期間を3年と定めています。平日は毎日着用するもの、あるいは汚れの頻度が高い通年服や作業服の交換タイミングは3年が目安といえます。
一方、使用頻度の低い防災服や丈夫なつくりの制服は5年が貸与期間です。
茨城県大子町の被服等貸与規則
茨城県大子町では、衛生作業をおこなう職員用作業衣の貸与期間を、上下ともに1年としています。浄化槽の清掃などの汚損の頻度が高い作業では、1年で交換するのが目安となるでしょう。
一方、汗や粉塵等の汚れ、摩擦が想定される土木事業用の作業衣の貸与期間は2年です。建設・工場の作業服の耐用年数1~3年と合致しています。
耐用年数以内でも買い替えが必要なケース
ウェアに次のような問題が生じたときは、改善・修繕が求められます。改善・修繕が難しい場合は買い替えが必要です。
-
ほつれ
-
穴・破れ
-
伸び縮み
-
パーツの不具合
-
臭い
-
汚れ
-
色褪せ
ほつれや穴、破れはひっかけによる事故につながるため、ただちに修繕が必要です。火気を扱う現場では、引火・やけどのリスクもあります。また、伸びた服は機械への巻き込み事故に、縮んだ服は動きにくさや露出した部分のケガにつながります。
ファスナーやボタンの不具合もよく確認しましょう。高所作業中にポケットのファスナーが開いてしまうと、落下物による事故を引き起こしかねません。ウェアのズレによる転落や転倒も考えられます。
臭い・汚れ・色褪せは企業のイメージに悪影響を与えます。洗濯やクリーニングなどで改善できない場合は、買い替えましょう。
作業服の寿命を縮める要素
愛着のある作業着をより長く着用するために、ウェアの寿命を縮めるNG行動を把握しておきましょう。
洗濯しない
洗濯頻度が低いと、繊維の隙間に入り込んだ汗や粉塵などの汚れによって機能が低下します。繊維の隙間が塞がることで通気性が低下したり、撥水コーティングの上に付着して効果を妨げたりするため、定期的に洗濯しましょう。
デスクワークであれば週に1回程度でも問題ありませんが、アクティブな作業をおこなう場合は毎回洗うのがベストです。
洗濯方法・干し方に問題がある
洗濯方法や干し方がウェアの寿命を縮める例は次のとおりです。
作業服は洗濯ネットに入れて洗うのが基本です。洗濯物同士の摩擦を低減できるほか、ファスナーやボタンなどが洗濯機にぶつかって破損するのを防げます。
柔軟剤は繊維をコーティングし、やわらかさを与える仕上げ剤です。手触りや香りは良くなりますが、繊維同士の隙間が狭くなり、加工の上に膜を作ってしまうため、通気性や吸水性、撥水効果が低下します。
アルカリ性洗剤は白い生地の染み抜きには有用ですが、染色した生地に使うと褪色を引き起こします。また、強力な洗剤なので繊維にダメージが生じることも少なくありません。撥水や防水などのコーティングを剥がすこともあります。
また、汗や埃、アルカリ性洗剤が残存した状態で紫外線に晒すと黄ばみが生じやすくなります。十分にすすぎをおこない、日陰かつ通気性の良い場所で干すのが理想的です。
詳しい洗濯方法は次の記事を参考にしてください。
収納・保管方法に問題がある
収納・保管方法にも注意が必要です。次の表を参考にしましょう。
畳んでしまうと折り目がしわとなって残りやすいため、見栄えがよくありません。とくに、複数枚を重ねてしまうと、重みでしわが強くなります。できれば、ハンガーにかけて収納しましょう。
ただし、ハンガーのサイズ選びは重要です。トップス・ジャケットの場合、肩のサイズに満たないハンガーを使うと、ウェアの重さによって食い込み、ハンガー跡が残ります。ボトムスも幅を合わせることで、しわを防げます。
保存場所にも気を配りましょう。干し方と同じく、直射日光が当たる場所や湿気が多い場所は避けるのが無難です。とくに、シーズンもののウェアを来年まで長期保管する場合は、場所の影響が顕著に出ます。
また、湿気が多い場所では、防水に使われるポリウレタンなどが加水分解をおこし、加工が剥がれてしまうこともあります。クローゼットの中などに除湿剤を入れて保管しましょう。
10万円未満の作業着に法定耐用年数はない
経理上の作業服の取り扱いに関する項目です。1着あたり10万円未満の作業着の勘定科目福利厚生費または消耗品費で、減価償却が必要な物品(減価償却資産)ではありません。
法定耐用年数は定められていないので、ウェアの機能としての耐用年数に関わらず、購入した年に全額を経費として計上しましょう。
一方、1着が10万円以上の場合は、工具器具備品(減価償却資産)として認められる場合があります。この場合の法定耐用年数は2年です。
適切な管理で作業服の寿命を長持ちさせよう
基本的には、作業服は3年以内に交換することを心掛けましょう。ただし、作業服の耐用年数は使用する環境・業務・素材・機能に左右されます。高温または火を扱う場所では、ウェアの寿命が1年未満になることも少なくありません。
また、解説した耐用年数はいずれも、適切に管理した場合の目安です。洗濯や干し方、保管方法に注意し、長持ちさせるよう努めましょう。
- 春夏向け作業着
- 空調服®・ファン付き作業着
- 作業着アウター・ジャケット
- 春夏向け長袖作業着シャツ
- 半袖作業着シャツ・七分袖シャツ
- 春夏向けコンプレッションウェア
- つなぎ
- スモック
- 春夏向けカーゴパンツ
- 作業着ショートパンツ・ハーフパンツ
- 春夏向けワークパンツ
- 秋冬向け・通年作業着・防寒着
- 防寒コート
- レインウェア
- 秋冬向けブルゾン
- 秋冬向けジャンパー
- 作業着スウェット・パーカー
- カーゴパンツ
- ワークパンツ
- アンダーウェア
- ワークエプロン
- 安全靴
- 長靴
- ヘルメット
- 秋冬向けアウター
- 秋冬向けポロシャツ
- 長袖作業着シャツ
- インソール
- 作業帽
- 防寒ベスト