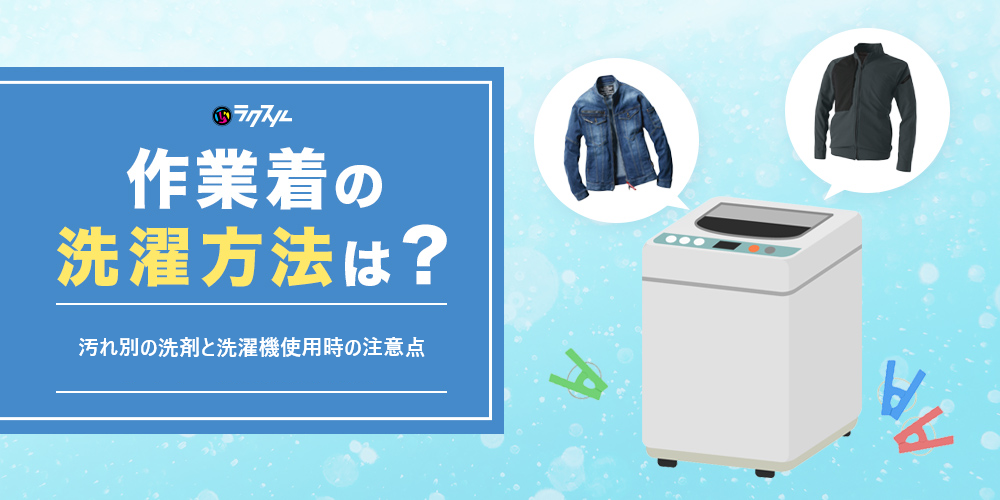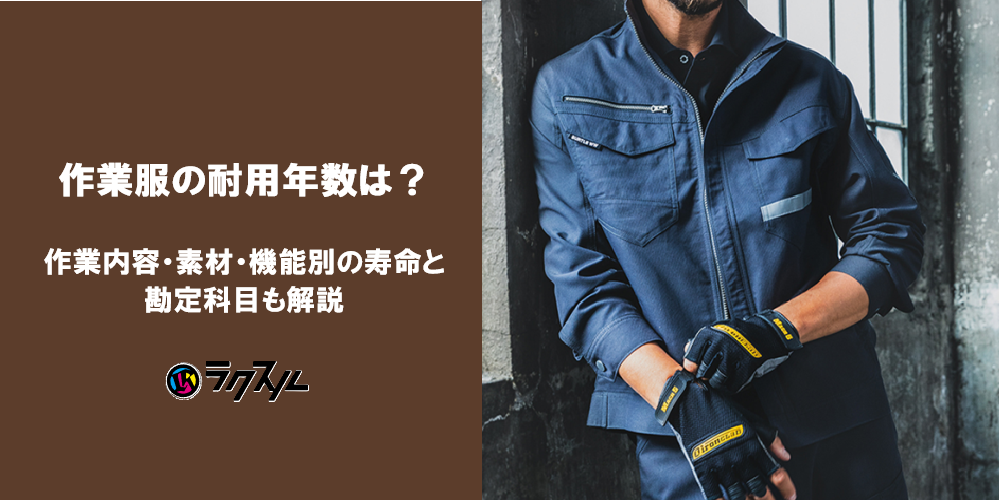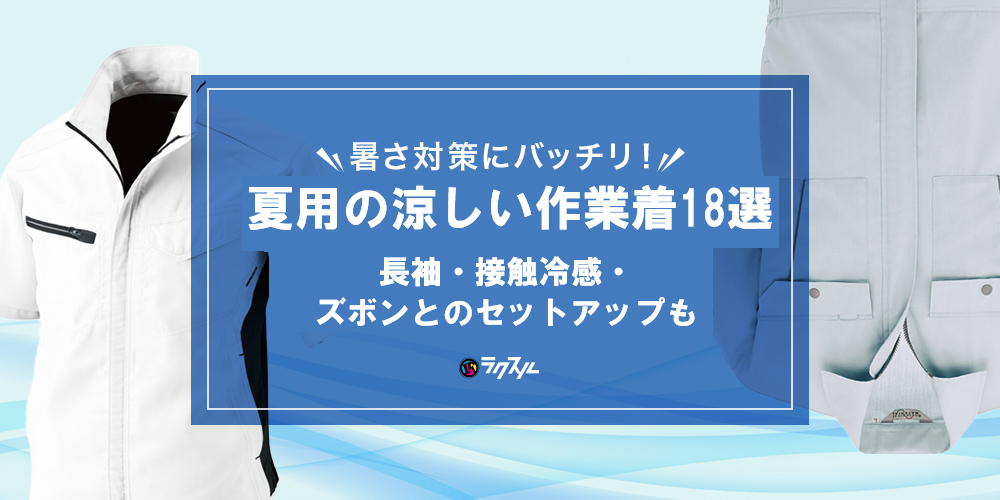建設現場や工場などで着用する作業着は、泥や油ですぐに汚れるのでこまめな洗濯が必要です。また、汚れが目立たない場合でも、汗など目に見えにくい汚れもあるでしょう。様々な種類の汚れに対して、どのように洗濯すべきか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、作業着の洗濯方法について詳しく解説します。汚れの種類別の洗い方や、洗剤の選び方、さらに洗濯時の注意点もご紹介します。お気に入りの作業着をケアして長く使いたい人は、ぜひ本記事をチェックしてみてください。
作業着の正しい洗濯手順
まずは、作業着の正しい洗濯手順について解説します。手順は大きくわけて4ステップありますので、順を追ってポイントを説明していきます。
1.固形汚れ・乾いた汚れを払い落とす
固形汚れや乾いた汚れは、まず払い落しましょう。水分を含んだ泥汚れは乾燥させてから、ブラシなどで掻き出してください。
とくに泥汚れが付いたまま洗濯機に入れてしまうと、繊維に染み込んで汚れを広げてしまいます。必ず事前に落としておきましょう。
2.頑固な汚れは浸け置きorもみ洗い
ブラッシングでも落ちない汚れには、浸け置き洗いやもみ洗いが効果的です。汚れたまま洗濯機に入れるとほかの衣類や洗濯槽を汚してしまうので、事前の浸け置き・もみ洗いが重要です。40〜50度のぬるま湯(※)を使うと汚れが落ちやすくなります。
もみ洗いをするときは、作業着をゴシゴシとこすりすぎないようにしましょう。強くこすると汚れを生地の奥にしみこませてしまったり、生地を傷めたりするためです。ピンポイントの汚れには、指先でつまみむようにして洗うと効果的です。
(※)血液汚れがある場合は、40度以下の水で一度洗う。血液は50〜60度で凝固し落ちにくくなってしまうため。
3.洗濯機で洗う
頑固な汚れを落とせたら、洗濯機を使いましょう。洗濯機は通常モードでOKです。
なお、洗濯槽に汚れが残っていると、次に洗濯機を使う際に汚れを移してしまう可能性があります。洗濯槽は定期的にメンテナンスを行い、きれいな状態を保っておきましょう。
洗濯ネットを使用する
作業着を洗濯機で洗う際は、なるべく洗濯ネットを使用してください。ファスナーやボタンなどのパーツでほかの衣類を傷つけないためです。また、撥水加工が施されてる場合も、摩擦で加工がはがれないようにネットに入れましょう。
4.風通しの良い場所で干す
洗濯が終わったら、風通しの良い場所で干しましょう。通気性が悪い場所で干すと生乾きになり、嫌なにおいが発生してしまいます。また、つなぎや長袖などの乾きにくい作業着は、肩幅を調節できるハンガーや物干しざおを使ってなるべく広げた状態で干してください。
作業着によっては、直射日光に当てると変色・劣化してしまうものもあります。特に、色の濃いものや多機能なものは、基本的に直射日光・紫外線NGです。下記のような洗濯表示を確認し、陰干し表示があるものは陰干しをしましょう。
【種類別】頑固な汚れの落とし方・洗剤
続いて、汚れの種類別に効果的な落とし方と、使うべき洗剤をご紹介します。5つのタイプの汚れについて解説しますので、状況に応じて洗濯方法を試してみてください。
泥・土汚れ
泥や土の汚れは乾かしてからブラッシングしましょう。泥汚れは繊維に小さな泥の粒が入った状態です。この泥の粒を搔き出すイメージでブラシをかけると、汚れが除去できます。水分があると落ちにくいので、十分に乾かしてからブラッシングしてください。
ブラッシング後は、洗濯用固形石鹸などでもみ洗いをしてから洗濯機にかけます。頑固な泥汚れは、あらかじめもみ洗いで汚れを落とすことがポイントです。固形石鹸がなければ食器用洗剤を使っても問題ありません。
油汚れ
作業着に付着する機械油は、お湯で溶かすのが効果的です。お湯に中性洗剤を溶かして浸け置きすると、油が溶けて落ちやすくなります。お湯の温度は40〜60度くらいで、浸け置きする時間は2時間程度が良いでしょう。
また、油汚れは酸性なのでアルカリ性で中和させる方法もあります。薄めた重曹水に浸け置きすることで、汚れが落ちやすくなります。ただし、作業着が色落ちしてしまうリスクもあるので注意が必要です。
サビ汚れ
サビ汚れには還元系漂白剤が効果的です。サビは鉄などから直接付着するほか、作業着についた金属片が酸化して発生する場合もあります。サビ汚れはまず汚れている部分を水洗いし、還元系漂白剤をしみこませてもみ洗いすると落ちやすくなります。
酸性は金属を溶かすので、お酢を使う方法もおすすめです。お酢と中性洗剤を混ぜ合わせたものをサビで汚れた個所にしみこませてしばらく置きます。その後、一度洗い流してから洗濯機にかけるときれいになります。
草汚れ
野外でついてしまう草汚れは、複数の成分からなる落としにくい汚れです。草の汁には油溶性と水溶性の汚れがあるので、まず油溶性の汚れから落とします。化粧品用クレンジングオイルや食器用洗剤で油溶性の汚れを溶かしましょう。その後、水で洗い流してください。
色素による汚れがどうしても落ちない場合は漂白剤を使います。時間がたつにつれて落ちにくくなってしまうので、早めの対処が必要です。色柄物の作業着の場合は、酸素系漂白剤を使うと色落ちしにくいのでおすすめです。
汗・皮脂汚れ
汗・皮脂汚れは毎日洗濯していれば問題ありませんが、放置すると黄ばみになってしまいます。蓄積した黄ばみ汚れは、ブラシによる部分洗いが効果的です。固形石鹼や中性洗剤をつけたブラシで襟元や脇など汚れが気になる箇所をこすり、洗い流しましょう。
汚れがひどく落ちない場合は、塩素系漂白剤に浸け置きする方法もあります。お湯に溶かした漂白剤に1〜2時間作業着を浸け、通常通り洗濯機にかけます。ただし、色落ちしやすいので色物や柄物にはおすすめできません。
洗濯する際の注意点
最後に、作業着を洗濯する際の注意点を解説します。ポイントは5点ありますので、作業着を洗う際に参考にしてみてください。
手洗いするときはゴム手袋を使う
手洗いを行う際はゴム手袋を使用しましょう。洗剤は素手で触れると皮脂も洗い流してしまうため、肌の乾燥や手荒れにつながります。酸素系・塩素系などの強い洗剤に限らず、中性洗剤などを使う場合でも手袋は必要です。
防水作業服は洗濯機が壊れる可能性
防水加工された作業服は、洗濯機が使えない場合があります。脱水時に作業着が水を通さないので、排水口が大量の水でふさがり洗濯機が故障しかねません。そのため、多くの防水作業服は洗濯機使用不可となっています。
下記の洗濯表示例を参考に、洗濯機が使えるかどうか確認しておきましょう。
防寒用は家庭洗濯不可のケースが多い
防寒機能を持った作業着は、家庭洗濯不可のものが多いので注意が必要です。特に中綿入りやファーがついた作業着は、家庭用の洗濯機では洗えません。下記の洗濯表示を確認し、洗濯できないものはクリーニング店に依頼しましょう。
柔軟剤による機能低下
撥水性・難燃性を持った作業着には、基本的に柔軟剤は使わないようにしましょう。柔軟剤が繊維をコーティングしてしまい、撥水・難燃の機能低下につながるからです。また、通気性の高い作業着も、柔軟剤が繊維の隙間をふさぐ可能性があります。
乾燥機は使用できない場合がある
乾燥機も作業着によって使用の可否が異なります。こちらも以下の洗濯表示を確認し、乾燥機を使って良いかチェックしておきましょう。
乾燥機NGの作業着もありますが、逆に撥水加工の場合、乾燥時の熱で撥水性が戻ることもあります。乾燥機OKの撥水性作業着は、乾燥機の使用がおすすめです。
汚れの種類に合った洗濯をして作業着を長く使おう
今回は、作業着の洗濯方法について解説しました。仕事内容によって様々な汚れがつく作業着は、毎日の洗濯が欠かせません。屋外なら泥や草汚れが、工場なら油やサビの汚れがついてしまいます。汚れの種類によって洗濯の仕方を変えることが重要です。
正しい洗濯方法を知ることで作業着は長く使えます。ぜひ、本記事の情報を参考にしていただき、お気に入りの作業着をケアしましょう。
- 春夏向け作業着
- 空調服®・ファン付き作業着
- 作業着アウター・ジャケット
- 春夏向け長袖作業着シャツ
- 半袖作業着シャツ・七分袖シャツ
- 春夏向けコンプレッションウェア
- つなぎ
- スモック
- 春夏向けカーゴパンツ
- 作業着ショートパンツ・ハーフパンツ
- 春夏向けワークパンツ
- 秋冬向け・通年作業着・防寒着
- 防寒コート
- レインウェア
- 秋冬向けブルゾン
- 秋冬向けジャンパー
- 作業着スウェット・パーカー
- カーゴパンツ
- ワークパンツ
- アンダーウェア
- ワークエプロン
- 安全靴
- 長靴
- ヘルメット
- 秋冬向けアウター
- 秋冬向けポロシャツ
- 長袖作業着シャツ
- インソール
- 作業帽
- 防寒ベスト