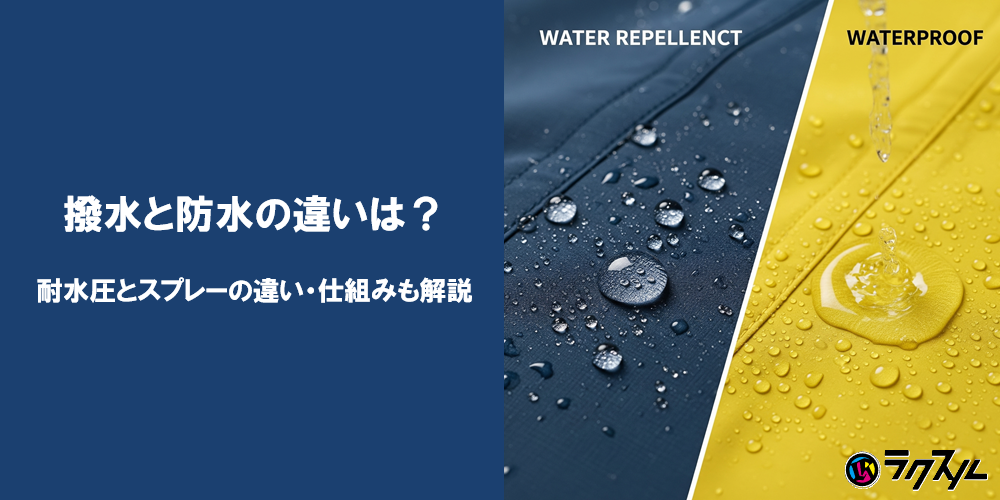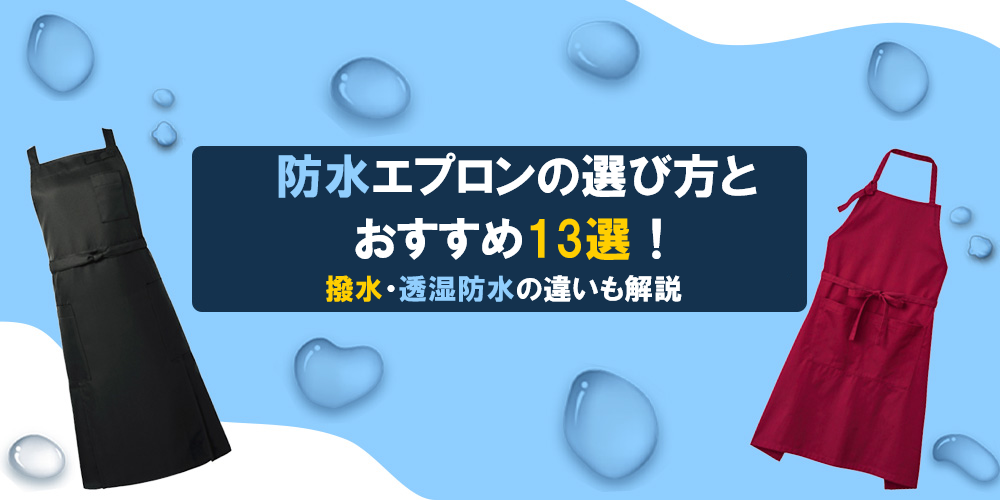撥水と防水はレインウェアをはじめとして、人や製品を水から守るために欠かせない機能です。しかし、イメージが似ているため混同してしまう人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、撥水と防水の違いを効果と仕組みから詳しく解説します。これを読めば、撥水機能と防水機能のレベルを見る基準(JISとIPX)、雪への対応までわかります。
また後半では、防水と耐水圧の関係、撥水スプレーと防水スプレーの仕組み、撥水・防水ウェアの取り扱いの注意点も解説します。ぜひ参考にしてください。
防水と撥水の違い
防水と撥水の主な違いは次のとおりです。それぞれを詳しく解説します。なお、防水に関しては衣服で用いられる「透湿防水」についても解説します。
防水とは
防水は水の分子を通さないこと、つまり水の侵入を物理的に蔽することです。密閉性の高い設計やコーティングによって、水が入り込む隙間を塞ぎます。長時間の防水に適しているため、雨の日の屋外作業や長時間の水濡れが想定される場面に向いています。
ただし、「防水=完全防水」というわけではありません。防水製品の中でも、水の量や勢い(水圧)次第では水の侵入を防げないものがあります。
なお、防水性能には耐水圧も深く関係しています。耐水圧については後半の「防水効果には耐水圧も関係」で詳しく解説します。
透湿防水とは
透湿防水は衣服で多くみられる機能で、雨などの外部の水はブロックしつつ、蒸れ(湿気)は逃がせるというものです。
水滴として存在する水分と空気中の水分の大きさの違いを利用することで、一見して相反する機能を実現しています。大きさの違いは次のとおりです。
なお、水の分子(H2O)の大きさは、0.38nm(=0.00038μm、注2)です。つまり、透湿防水は水分子を通さないということではありません。
(注1)μm:マイクロメートル
(注2)nm:ナノメートル、1nmは1μmの1,000分の1
撥水とは
撥水は水滴を玉状に弾く機能で、衣服においては、皿洗いや水やりなどの一時的な水ハネへの対応に向いている機能です。
撥水加工では液体の表面張力の原理を利用しています。表面張力は、液体の分子が互いに引き合うことで、できるかぎり表面積を小さくしようとする性質です。表面張力が大きいほど、液体は球形に近づきます。
撥水性が生じるのは、液体と固体の表面張力が次の状態にあるときです。
生地などの固体表面の表面張力が液体の表面張力よりも小さい場合、液体が固体に付着しても球形を保って弾かれ、転がり落ちます。これが撥水性です。
撥水加工では、固体表面の表面張力が小さくなるよう工夫されています。代表例はフッ素加工で、表面張力が非常に低いフッ素樹脂でコーティングすることで液体を弾いています。
ただし、防水とは違って物理的に水分を遮蔽しているわけではありません。そのため、液体を押し込もうとする力(水圧など)がはたらくと、玉状に弾けずに水分が侵入することがあります。防水性としては一時的で、長時間水にさらされる場には向いていません。
防水と撥水の効果をあらわす基準
防水性と撥水性のレベルを確認したいときに役立つ基準として、撥水効果を示すJIS規格と防水効果を示すIPXという指標を解説します。
撥水効果の基準はJIS L 1092
日本産業規格(JIS)が定めた撥水効果の基準はJIS L 1092「繊維製品の防水性試験」です。この試験では防水性も定められていますが、防水に関しては国際基準のIP規格に置き換えられているため、次の項目で詳しく解説します。
撥水に関するJIS L 1092の試験は、生地に水をスプレーし、軽く水を払った後で生地に残った水滴の量を確認するというものです。
なお、洗濯やドライクリーニングをしても撥水性能が変わらないことを謳う製品の場合は、生地を洗濯またはドライクリーニングした上で試験します。
評価は1~5級あり、級数が大きいほど撥水効果が高いことを示しています。詳細は次のとおりです。
なお、一般的なレインコートで撥水性があることを表示するためには、撥水度が2級以上である必要があります。1級の場合は繊維製品品質表示規程により、撥水性を表示できません。
防水効果の基準はIPX
IPXは防塵・防水等級を示す国際規格で、「IP68」のように記載します。画像のように、IPの次に続く数字が防塵等級、防塵等級の次の数字が防水等級です。製品を試験していない機能は「X」と記すため、防水性能は「IPX8」のように記載します。
防塵性能は0~6等級、防水性能は0~8等級で評価されます。等級別の防水の程度は次の通りです。
IP0は水の侵入を防ぐことができない製品です。IPX1は垂直に落ちる水に対してのみ防水性があります。無風かつ小雨であれば水の侵入を防ぐことができるでしょう。IPX2とIPX3は垂直に落ちる雨以外でも対応できます。
IPX4~IPX6は水が当たる角度を問わず防水性を発揮できるレベルです。水の量・勢いによって段階が分かれています。レインコートなどの一般的な衣服の場合はIPX6であれば最強クラスです。
IPX7は水面下15~100cm相当の圧力で30分間、水中に没しても水が侵入しないレベルです。IPX8は細かく規定されていませんが、IPX7より厳しい条件かつ受渡当事者間の協定で定めた試験をクリアしたものが該当します。海や湖等への潜水を前提とした製品向けです。
なお、IP規格は国際規格ですが、日本では日本産業規格のJIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」でIP規格を用いることを記しています。
防水効果には耐水圧も関係
衣服の防水効果を確認するときは、耐水圧にも注目しましょう。耐水圧はどの程度の雨でも耐えられるかを測る指標です。1cm四方の生地(素材)に水柱を押し当てて、裏側に染みるまでの水量を測ることで測定されます。
耐水圧の数値と耐えられる雨のレベルは次のとおりです。
ただし、雪の日は降雪量に関わらず耐水圧10,000mm以上、登山では降雨量に関わらず20,000mm以上が推奨されています。雪は衣服の上に残りやすいため浸水しやすく、登山は浸水が体温低下につながり、命に関わるためです。
また、濡れた接地面に座ったり、膝をついたりしたときは人の体重分の圧力で浸水することがあります。体重75kgの人の場合の圧力は次のとおりです。
-
座ったときの圧力:約2,000mm
-
ひざまづいたときの圧力:約11,000mm
つまり、耐水圧10,000mのレインウェアを着用し、天気が小雨だった場合でも、濡れた地面で膝をつけば、膝にかかる圧力が耐水圧を超えるため、膝部分から浸水する可能性があるということです。
同様の理由で、リュックを背負ったときなどの局所的な圧力によっても、浸水することがあります。
なお「撥水加工」の耐水圧は、加工の有無に関わらず生地そのものの耐水圧によります(撥水加工自体に耐水圧はない)。
防水スプレー・撥水スプレーの仕組みと効果
一般的な撥水スプレー・防水スプレーに関しては「撥水」と「防水」とが同じ意味です。
本来であれば「防水」は水を物理的に遮蔽することを指しますが、スプレーの場合は撥水コーティングによって一時的な防水性をもたせるレベルに留まります。水の侵入を防ぐほどの被膜をスプレーで形成することは難しいからです。
撥水スプレーには、表面張力が小さい撥水成分が含まれています。撥水成分はフッ素系とシリコン系の2種類が主流ですが、近年は炭化水素系も登場しています。3種類の違いは次のとおりです。
フッ素系は摩擦に弱く持続性は劣る面がありますが、撥水・撥油効果が最も優れています。しかし、海外では健康や環境への問題点が懸念される有機フッ素化合物が使われるケースがあり、規制の対象になっている場合があります。
日本で販売されている製品では問題のある成分は使われていませんが、フッ素系では未知な部分もあるため、代替製品の開発が検討されている状況です。現時点で存在する代替製品としては、シリコン系や炭化水素系があげられます。
ただし、シリコン系には撥油性がなく、染みになりやすいため革製品には使えません。炭化水素系は健康・環境面の負荷が少ない点がメリットですが、撥水性は劣ります。どのタイプも一長一短あるため、目的に応じて選びましょう。
効果の持続性を重視するなら防水・撥水ウェア
レインウェア
作業着(ジャケット・パンツ)
ウインドブレーカー
飲食・サービス用エプロン
医療・介護用エプロン
バッグ
安全靴・スニーカー
長靴
防水・撥水ウェアの注意点
防水・撥水ウェアを安全に長く使うための注意点を解説します。
洗濯時は柔軟剤を使わない
防水・撥水ウェアを洗濯するときは、柔軟剤を使わず中性洗剤だけで洗いましょう。防水・撥水効果をもつ被膜を柔軟剤でコーティングすることになるため、生地の表面張力が強くなり、機能が低下する可能性があるからです。
アルカリ性・酸性洗剤NG
防水・撥水ウェアは基本的には中性洗剤で洗うことを前提に設計されているため、アルカリ性・酸性洗剤を使うのはやめましょう。アルカリ性成分、酸性成分がウェアの被膜を剥がす可能性があります。
ただし、中性洗剤でも粉洗剤は避けるのが無難です。粉が溶け切らずに繊維の間に入ったり、研磨としてはたらいてしまうと、防水被膜や撥水コーティングの効果を十分に発揮できなくなります。
乾燥機の使用は洗濯表示を確認
防水・撥水ウェアの中には熱風によって撥水性が復活するものがありますが、すべてではありません。生地の性質以外の点で乾燥機NGの場合もあるので、必ず洗濯表示を確認してください。以下は2024年8月20日以降に生産された衣服の洗濯表示です。
消費者庁「洗濯表示(令和6年8月20日以降)」
直射日光が当たる場所で乾かさない
撥水加工は紫外線で劣化する傾向があるため、直射日光下で干すのはおすすめしません。また、アウトドア用の防水・撥水ウェアで使われることの多いナイロンは、紫外線で変色することがあります。
洗濯表示の「自然乾燥処理の記号」で、四角の左上の角に斜めの線が入っているものは、日陰干しを推奨しています。以下は2024年8月20日以降に生産された衣服の洗濯表示です。
消費者庁「洗濯表示(令和6年8月20日以降)」
なお、「ぬれつり干し」「ぬれ平干し」などの「ぬれ干し」は脱水せずに濡れたまま干すことを指します。
濡れたまま長期間放置しない
撥水・防水であっても、長時間の水濡れに強いわけではありません。とくに防水加工で使われるポリウレタンコーティングは、長期間水にさらされると加水分解という反応を起こす可能性があるため要注意です。
加水分解は、水と他の物質が反応して物質を分解する化学反応で、プラスチックやゴム製品を劣化させます。べたべたしたり、白っぽく変色していれば加水分解による劣化です。ひび割れや剥がれも生じるため、防水性能が低下します。
防水ウェアは洗濯機の脱水NG
防水ウェアへの影響ではなく、洗濯機への影響という点で脱水はNGです。
脱水モードでは、衣服が含んだ水分を遠心力によって絞るために、洗濯槽が高速回転を始めます。このときに防水ウェアが洗濯機の排水穴を塞ぐと水の排出がおこなわれず、大量の水とともに洗濯槽が高速回転することになります。
回転によって水の動きが変わるため、バランスを崩して洗濯機が転倒・故障する恐れがあります。製品評価技術基盤機構(nite)がおこなった実験では、自転車カバーを脱水しようとした洗濯機が回転しながら転倒しました。
自宅の場合、洗濯機が転倒することで周囲の防水パンや洗面台、浴室の扉の破損などにつながるリスクもあります。防水ウェアも同様の危険性があるため、脱水しないよう気を付けましょう。
防水・撥水に関するQ&A
最後に、防水・撥水に関する質問4つに回答します。
Q.防水・撥水加工は雪も防げますか?
A. 防水ウェアなら耐水圧10,000mm以上で雪に対する防水効果を期待できます。撥水加工は、雪の付着を落としやすくはなりますが、長時間雪が付着している場合は浸水する可能性があります。
Q.防水・撥水効果はどれくらいの期間続きますか?
A. 防水ウェアの寿命は3~5年が目安、撥水ウェアの寿命は1カ月から数年といわれています。ただし、管理方法次第では目安の期間よりも短くなる場合があります。
例外はアウトドア用ウェアでよく使われる素材「GORE-TEX(ゴアテックス)」で、基本的には寿命がありません(永続的)。
なお、撥水・防水スプレーの効果継続期間は、1~2カ月が目安です。
Q.ウォータープルーフは防水と撥水のどちらですか?
A. ウォータープルーフ(waterproof)は基本的には「防水」の意味です。ただし、化粧品等においては汗や水に強いことを表すため、必ずしも耐水圧をもつ防水機能をもつとは限りません。なお、撥水の英語は「water repellent」です。
Q.防水の生地・素材にはどんなものがありますか?
A. 防水素材には次のようなものがあります。
-
TS TEX
-
GORE-TEX(ゴアテックス)
-
eVent(イーベント)
-
Omni-Tech(オムニテック)
-
Pertex Shield(パーテックスシールド)
-
Dermizax(ダーミザクス)
-
HYVENT(ハイベント)
この他、ナイロンやポリエステルをポリウレタン(PU)コーティングしたものなどがあります。
撥水・防水の違いを知って使い分けよう
撥水加工は皿洗いや水やりのシーンにおける、一時的な水ハネに対応できる機能です。一方、防水加工なら雨の日の長時間作業でも対応できます。とくに耐水圧が高いものなら、嵐や雪の日でも水の侵入を防げます。シーンに応じて使い分けましょう。
ただし、撥水・防水スプレーはどちらも撥水の意味であり、効果は一時的かつ短期間であるため、衣服の性能と同じように考えることはできません。水濡れする機会が頻繁であれば、撥水・防水ウェアの導入をおすすめします。
商品を選ぶときは、撥水の基準JIS L 1092や防水の基準IPXが参考になります。また、お気に入りのウェアが見つかったときは、長く使い続けるためにも適切なケア・管理を心掛けましょう。ぜひ今回ご紹介した注意点を参考にしてください。
- 春夏向け作業着
- 空調服®・ファン付き作業着
- 作業着アウター・ジャケット
- 春夏向け長袖作業着シャツ
- 半袖作業着シャツ・七分袖シャツ
- 春夏向けコンプレッションウェア
- つなぎ
- スモック
- 春夏向けカーゴパンツ
- 作業着ショートパンツ・ハーフパンツ
- 春夏向けワークパンツ
- 秋冬向け・通年作業着・防寒着
- 防寒コート
- レインウェア
- 秋冬向けブルゾン
- 秋冬向けジャンパー
- 作業着スウェット・パーカー
- カーゴパンツ
- ワークパンツ
- アンダーウェア
- ワークエプロン
- 安全靴
- 長靴
- ヘルメット
- 秋冬向けアウター
- 秋冬向けポロシャツ
- 長袖作業着シャツ
- インソール
- 作業帽
- 防寒ベスト