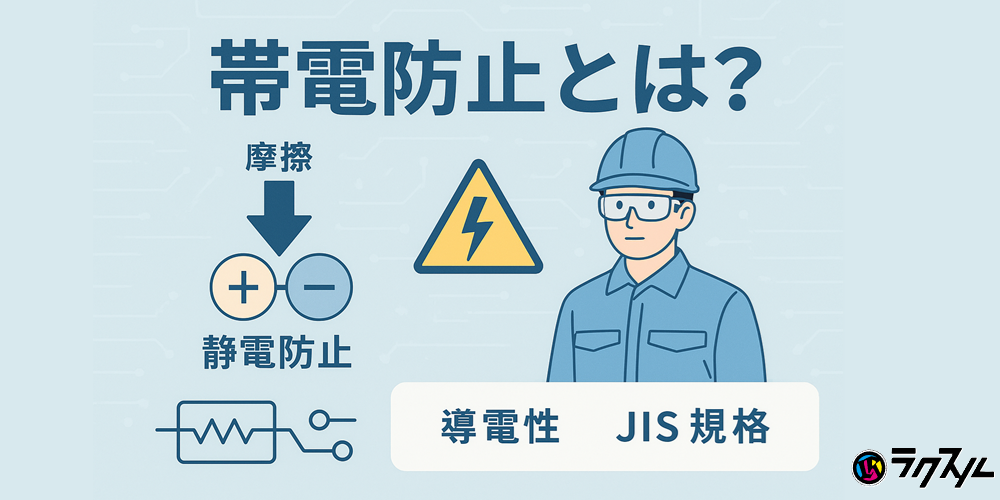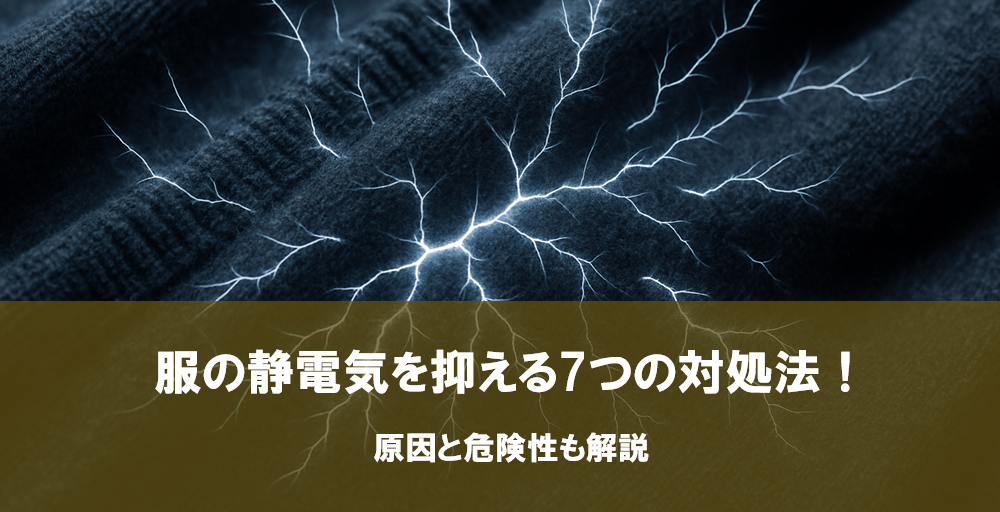帯電防止加工や素材は、静電気による引火や精密機器の故障が懸念される場所で用いられます。しかし、実際にどのようなものなのかをイメージできる人は少ないのではないでしょうか。
そこで本記事では、帯電防止とは何かを帯電・静電気の意味から詳しく解説します。関連用語として、静電防止や導電性、帯電防止域の意味なども解説するので、ぜひ参考にしてください。後半では帯電防止ウェアや安全靴も登場します。
帯電防止とは
まずは帯電と帯電防止、静電防止の意味を解説します。
帯電とは
帯電は文字通り、物質が電気を帯びている状態を指しますが、具体的には物質が持っているプラスとマイナスの電気のバランスが崩れて、静電気を帯びた状態のことです。
物質にはプラスの電気を持つ原子核とマイナスの電気を持つ電子があります。物質が単体で存在するときには、プラスとマイナスのバランスがとれた、電気的に中性の状態(=電気を帯びていない状態)です。
しかし、異なる物質同士の摩擦や接触などが生じると、電子が片方へ移動することがあります(上図参照)。この、電子の移動によってバランスが崩れた状態を「静電気」と呼び、静電気を帯びていることを「帯電」と呼びます。
一般的に感じる「静電気」は電子の移動による放電
帯電している物質はプラスとマイナスの電気のバランスが崩れているため、他の物質と接触したときに、中性の状態に戻ろうとします。このときにおこなわれる電子の移動が、バチッとするような放電となって現れます。
一般的に「静電気」と呼んでいるものは、静電気を帯びたものが生じさせる放電です。
帯電防止は静電気を防ぐこと
帯電防止は物質のプラスとマイナスのバランスが崩れる状態(静電気)を防ぐことを指します。静電気を防げれば帯電防止に当てはまるため、電気をほとんど通さないことで静電気を防ぐものと、電気を素早く逃がすことで静電気を防ぐものの両方が存在します。
帯電防止と静電防止はほぼ同じ意味
静電防止の「静電」は「静電気」のことです。帯電防止が静電気を防ぐものであるため、帯電防止と静電防止はほぼ同じ意味です。
帯電防止と導電性の関係
帯電防止加工が施されたウェアやマットなどには、導電性の高い金属やカーボンなどが使われる傾向にあります。帯電防止と導電性の関係を解説します。
導電性が高いものを用いる帯電防止加工
金属に触れると静電気を逃がせると聞いたことがある人もいるでしょう。これは金属に電気を通しやすい性質(導電性)があるためです。導電性が高い物質の代表例は次の通りです。
-
銀
-
銅
-
金
-
アルミニウム
-
ポリアリニン(導電性ポリマー)
-
ポリアセチレン(導電性ポリマー)
-
カーボン
-
グラファイト
金属や導電性ポリマー(導電性高分子)は導電性が高い物質(導体)です。
導体は電気を通しやすいため、摩擦などの帯電しやすい状況にあっても、素早く電子を放出することで電気のバランスを保ちます。これが帯電防止の衣服やマットに導体を用いる理由です。
ガソリンスタンドの静電気除去シート
ガソリンスタンドに設置されている静電気除去シートは、放電によるガソリンの引火を防ぐためのものです。プラスチックと導電性の高い金属を混ぜて作られています。
車のシートと衣服の摩擦によって利用者が帯電していても、静電気除去シートに触れれば電子を放出できるため、引火のリスクを低減できます。
電気抵抗における帯電防止域
衣服やマットにおける帯電防止は、導電性の高い素材を活用して放電する加工を指します。一方、電気抵抗における「帯電防止」は、電気を通しにくい性質を指しています。次の表をご覧ください。
帯電防止域の物質は帯電防止プラスチックなどで、一般的なプラスチック(絶縁体)と比べると電気をある程度は通す性質を持ったものです。帯電防止加工の衣服やマットとは異なるものであることがわかります。
なお、水は不純物が含まれない「純水」の場合は電気を通さない絶縁体です。ミネラルなどの不純物が含まれたときに、導電性が高くなります。
帯電防止技術
帯電防止技術には次のようなものがあります。
-
界面活性剤
-
高分子型帯電防止剤
-
導電性素材の使用
界面活性剤には親水性があり、空気中の水分を利用して物質の表面に水(※)の膜を形成します。電気を通しやすい水が電子(マイナスの電気)を素早く放出することで、帯電を防ぐ仕組みです。ただし、乾燥しているときには効果が薄いというデメリットがあります。
高分子型帯電防止剤は金属イオンを用いて、電気を通しやすくするものです。帯電防止の仕組みは界面活性剤と似ていますが、湿度には左右されません。ただし、界面活性剤と比べると高コストです。
カーボンや金属などの導電性の素材を練りこんだり、塗布したりすることで電気を素早く逃がす方法もあります。衣服やフロアマットなどで採用されやすい方法です。
(※)空気中の水分は不純物を含んでおり、電気を通しやすい
帯電防止の作業着は制電作業着
帯電防止加工が施された作業着は「制電作業着」と呼ばれており、大きく分けて次の2種類があります。
-
一般的な制電作業着
-
JIS規格適合の制電作業着
それぞれの違いを解説します。
一般的な制電作業着
一般的な制電作業着は界面活性剤を塗布したものが中心です。帯電防止性は服のまとわりつきや埃・髪の毛の付着を防ぐレベルといえます。動きやすさや衛生面の観点から施される帯電防止加工です。エプロンやコックコート、清掃用の作業服などで用いられます。
JIS規格適合の制電作業着
建設・製造などの現場では、引火事故や静電気による機器の故障を防ぐために、JIS T8118規格適合の作業服の着用が求められます。JIS T8118の規定は次のとおりです。
-
生地の帯電電荷量が7μC/m2以下(導体を使用)
-
帯電防止ではない裏地の露出面積は20%以下
-
裏毛生地(ボア)は使用不可
-
ボタン・ファスナーなどの金属製付属品は露出させない
-
作業着1点当たりの帯電電荷量が0.6μC以下
このような、JIS T8118では帯電防止性能が厳格に規定されています。また、繰り返しの洗濯や摩擦でも性能が低下しないことを示す試験を経て合格したものだけが、JIS適合の制電作業着として認められます。
帯電防止ウェアの種類
最後に、帯電防止ウェアの種類を業界ごとに紹介します。
建設・製造
作業ジャケット・ズボン
安全靴
ヘルメット
医療・看護・介護
スクラブ
白衣
介護用エプロン
飲食・サービス
エプロン
コックコート
シーンに応じた帯電防止性が重要
帯電防止は物質が持つプラスとマイナスの電気のバランスが崩れるのを防ぐ、静電気防止であることがわかりました。作業服をはじめとする衣服では、導電性の高い素材を使った帯電防止加工が採用されています。
ただし、すべての帯電防止加工が引火や精密機器の故障を防げるわけではありません。ガソリンなどの揮発性・引火性の高いものや、精密機器を扱う現場ではJIS T8118適合の制電服を選びましょう。
- 春夏向け作業着
- 空調服®・ファン付き作業着
- 作業着アウター・ジャケット
- 春夏向け長袖作業着シャツ
- 半袖作業着シャツ・七分袖シャツ
- 春夏向けコンプレッションウェア
- つなぎ
- スモック
- 春夏向けカーゴパンツ
- 作業着ショートパンツ・ハーフパンツ
- 春夏向けワークパンツ
- 秋冬向け・通年作業着・防寒着
- 防寒コート
- レインウェア
- 秋冬向けブルゾン
- 秋冬向けジャンパー
- 作業着スウェット・パーカー
- カーゴパンツ
- ワークパンツ
- アンダーウェア
- ワークエプロン
- 安全靴
- 長靴
- ヘルメット
- 秋冬向けアウター
- 秋冬向けポロシャツ
- 長袖作業着シャツ
- インソール
- 作業帽
- 防寒ベスト