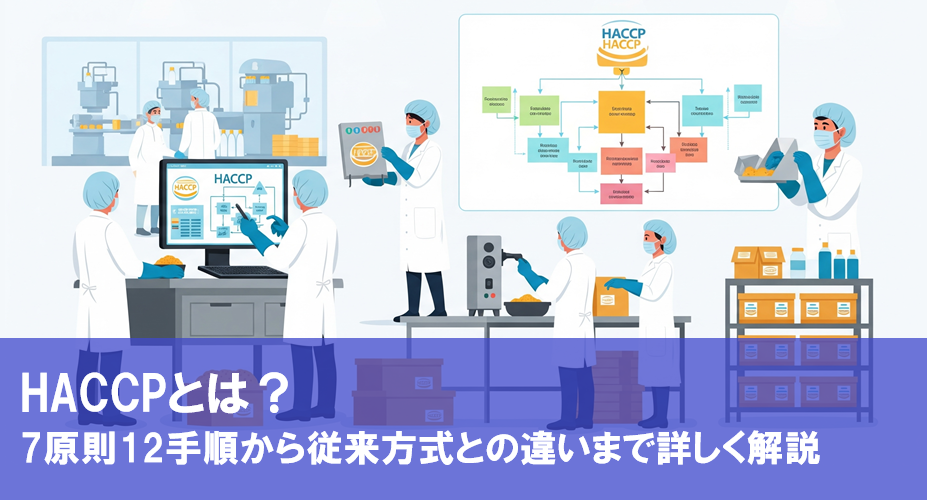HACCPは2021年6月1日に義務化された、食品の衛生管理方法です。義務化から数年が経過していますが、食品業界に新規参入する人にとっては、わかりづらい部分も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、HACCPとは何かを読み方から詳しく解説します。従来の衛生管理方法との違いや7原則12手順までわかります。併用される一般的な衛生管理方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
HACCPとは
HACCPの読み方と正式名称
HACCPは「ハサップ」と読みます。正式名称は「Hazard Analysis and Critical Control Point」です。それぞれの単語の意味は次の通りです。
-
Hazard:危害(危害要因)
-
Analysis:分析
-
Critical:重要
-
Control:管理
-
Point:点
HACCPの概要を含めた詳細は次のとおりです。
HA(Hazard,Analysis):危害要因分析
原材料由来や製造過程で生じるHazard(危害要因)は次のようなものです。
-
有害物質による汚染
-
異物混入
-
微生物・細菌の繁殖
このような危害要因を予測し、管理方法を明確化・ルール化することがHA(危害要因分析)です。分析結果に基づいて、CCP(重要管理点)を設定します。
CCP(Critical Control Point):重要管理点
CCPは食品製造における重要管理点です。加熱・冷却工程における温度管理と、包装時の異物検出などがあげられます。
また、CCPとは別に継続的な監視と記録の方法も設定します。万が一問題が発生したときに、どの時点でどのような変化によって問題が生じたかを迅速に明らかにするためです。
HACCPと従来の衛生管理の違い
従来の抜き取り検査方式とHACCP方式の違いは次のとおりです。
従来の衛生管理では食品の製造から包装までの衛生管理基準・手順はメーカーに一任されており、包装したものを抜き取り検査することで食品の安全性を監視していました。そこで問題が発覚した場合は出荷を停止・商品を回収する対処的な方式です。
しかし、従来の抜き取り検査では、サンプル以外の製品の問題を発見できないため、検査漏れのリスクがありました。また、問題発覚後に「どの工程で問題があったか」を検証する手間がかかるほか、出荷停止・商品回収のコストが大きいという問題もありました。
一方のHACCPは予防的手法です。各工程において基準を設けて管理できるため、問題のある製品を大量に製造してしまう状況を防げます。問題がある製品が消費者に届くのを防げるほか、出荷停止・商品回収・破棄にかかる膨大なコストを削減できるということです。
検査工程の手間や人員増による導入コストの増大はデメリットですが、「安全な食品の提供」というブランディングも含めると、HACCPは企業にとっても有益な衛生管理方法といえます。
HACCPの7原則12手順
HACCPは、1993年にCodex(コーデックス、国際食品規格)委員会が策定した7原則12手順に準拠します。詳細は次のとおりです。
上記のように、手順6~12が原則1~7と同じ項目を指します。手順1~5は原則を実施するための準備に該当する部分です。
HACCPという単語自体はHAとCCPのみに触れていますが、実際はモニタリングや検証を含めた12手順によって衛生管理を実施することがわかります。
事業者によってHACCPの衛生管理が異なる
日本では令和3年(2021年)6月1日からHACCPに沿った衛生管理が義務化されましたが、事業者の業種や規模によって、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に分かれます。それぞれを詳しく解説します。
HACCPに基づく衛生管理
「HACCPに基づく衛生管理」は主に大規模事業者を対象とした衛生管理レベルです。HACCPの7原則に基づいた計画と衛生管理を、事業者自らが設定して実施することが求められます。使用する原材料や製造方法に応じて衛生管理を最適化するためです。
参考:厚生労働省「HACCPに基づく衛生管理」
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」は業界団体が作成し厚生労働省が確認した手引書の内容を実施すれば達成できるものです。「HACCPに基づく衛生管理」とは違い、事業者自らが設定する必要はありません。小規模な事業者の例は次のとおりです。
参考:厚生労働省「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」
対象外の食品等事業者
HACCPは原則としてすべての食品事業者を対象としますが、下記に該当する場合は対象外です。
-
農業・水産業における採取業
-
食品または添加物の輸入業
-
食品または添加物の貯蔵・運搬(冷凍、冷蔵倉庫業を除く)
-
常温で長期保存可能な包装食品の販売業
-
器具容器包装の輸入または販売業
-
1回の提供食数が20食程度未満の集団給食施設
具体的には、農家や漁師などの採取業、スナックや缶詰などの常温保存可能な食品の輸入・仲卸・小売りなどは対象外といえます。
参考:厚生労働省「HACCP(ハサップ)」
業界別HACCPの手引書
小規模事業者向けの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」では、各業界団体が作成した業界別の手引書があります。厚生労働省が公開している手引書は115種類あるため、その一部を列挙します。
-
公益社団法人 日本食品衛生協会「小規模な一般飲食店:詳細版」
-
一般社団法人 日本食品添加物協会「食品添加物製造(50名未満)」
-
一般社団法人 日本食品添加物協会「食品添加物製造(ガス充填)」
-
全国乾麺協同組合連合会「機械製乾めん・手延べ干しめん製造」
-
全国納豆協同組合連合会「納豆製造:手引書」
-
日本豆腐協会「豆腐類製造事業者向け/豆腐・豆乳・オカラ編」
-
全国穀類工業協同組合「米粉等製造」
-
全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会「魚肉ねり製品製造(小規模な魚肉ねり製品事業者向け)」
-
一般社団法人日本食鳥協会「認定小規模食鳥処理場」
これらの手引書は厚生労働省のサイト「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のページにある「食品等事業者団体が作成した業種別手引書」からアクセスできます。表紙または50音順で探しましょう。
HACCPは「一般的な衛生管理」と併用する
食品等事業者には、「HACCPに沿った衛生管理」と同時に「一般的な衛生管理」に関する基準に基づく衛生管理が求められます。ここでは、一般的な衛生管理の概要と14の基準を解説します。
一般的な衛生管理とは
一般的な衛生管理とは、食品の安全性を確保するために必要とされる基本的な衛生管理のことです。施設と従業員の清潔の保持だけでなく、温度管理や従業員への教育も含めた14項目の基準が設けられています。
ただし、具体的な方法には踏み込まない「概念」を示したものであるため、具体的な計画・手順の作成が必要です。この計画と手順(一般衛生管理プログラム)はPRP(Prerequisite Programs)と呼ばれます。
一般的な衛生管理の14の基準
引用:厚生労働省「一般的な衛生管理に関する基準」
1番目の食品衛生責任者に立てるのは、食品衛生管理者や調理師等の資格もつ人、あるいは資格要件を満たす人、または自治体が実施する養成講習会を受講した人に限られます。その管理者の下で徹底される衛生管理・教育基準が2番目以降で定められています。
衛生管理においては、細菌やカビの繁殖を抑えるための清掃・消毒などの具体的な取り組みを計画・実施することが必要です。機器の部品交換を含むメンテナンスも異物混入を防ぐための計画に含まれます。
なお、項目の多くは衛生の保持に関わる事項ですが、9番の消費者に対する情報提供や14番の記録も重要なポイントです。万が一の際に迅速に情報を開示し、被害拡大を防いで再発を防止することが求められます。
HACCPを導入しなかった場合の罰則
HACCP義務化の対象となる食品関連事業者では、HACCPを導入できていないと、食品衛生法または都道府県の条例違反となり、罰則の対象となる場合があります。
保健所の営業許可の更新あるいは通常の定期立ち入り検査で違反が発覚すると、罰則となる可能性があるため、HACCPによる衛生管理と記録の保持を適切に実施しましょう。
HACCPを遵守して食の安全を守ろう
HACCPは2021年6月1日に義務化された衛生管理方法です。施行後の経過措置期間は過ぎているため、これから新に参入する事業者も、HACCPを遵守する必要があります。
工程ごとの管理・記録が必要であるため、導入コストはかかりますが、問題のある商品を大量製造するリスクを低減できることは大きなメリットです。また、消費者に対して安心感をもたらすブランディングの点でも、企業にとって有益な方式といえます。
HACCPに対応するユニフォームへの変更なども含めて、ルールを遵守した適切な衛生管理を計画・実施しましょう。
- 春夏向け作業着
- 空調服®・ファン付き作業着
- 作業着アウター・ジャケット
- 春夏向け長袖作業着シャツ
- 半袖作業着シャツ・七分袖シャツ
- 春夏向けコンプレッションウェア
- つなぎ
- スモック
- 春夏向けカーゴパンツ
- 作業着ショートパンツ・ハーフパンツ
- 春夏向けワークパンツ
- 秋冬向け・通年作業着・防寒着
- 防寒コート
- レインウェア
- 秋冬向けブルゾン
- 秋冬向けジャンパー
- 作業着スウェット・パーカー
- カーゴパンツ
- ワークパンツ
- アンダーウェア
- ワークエプロン
- 安全靴
- 長靴
- ヘルメット
- 秋冬向けアウター
- 秋冬向けポロシャツ
- 長袖作業着シャツ
- インソール
- 作業帽
- 防寒ベスト