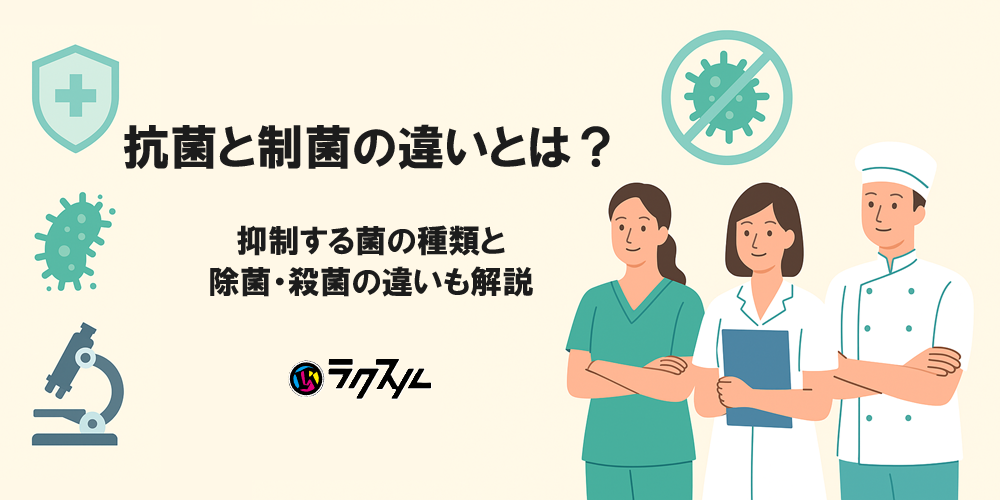抗菌・制菌はユニフォームで表記される衛生機能のひとつです。しかし、「菌に効きそう」というイメージはあっても、対象とする菌や効果の程度までは知らないという人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、抗菌と制菌の意味と対象とする菌の違いを詳しく解説します。類似の単語である殺菌・消毒・滅菌・静菌の意味と使われる製品の違い、衣類における抗菌・制菌の認証制度SEKマークの詳細も解説するので、ぜひ参考にしてください。
抗菌・制菌・除菌・殺菌の違い
ここでは、抗菌・制菌との違いに加え、類似の除菌・殺菌などとの違いを詳しく解説します。
抗菌・制菌は菌の繁殖を抑制すること
抗菌・制菌は付着した菌が繁殖するのを抑制する機能です。布製品の場合は繊維に銀イオンなどの抗菌剤が練り込まれます。抗菌剤には次のような種類があります。
なお、銀イオン自体には細菌の代謝を阻害して死滅させる効果がありますが、製品における抗菌・制菌はあくまでも「増殖を抑制する」ことを目的とした機能です。
ただし、医療現場における「抗菌」は殺菌・滅菌・消毒・静菌を総括する用語としても使われるようです。
静菌
「静菌」も菌の増殖を抑制することを指しますが、食品や化粧品で使われる用語(食品衛生法)です。
また、抗菌や制菌加工でつかわれる抗菌剤は殺菌作用を持つものがありますが、静菌というときには基本的に、殺菌作用は含みません。菌を殺さずに増殖を抑制するという概念です。
殺菌は菌を殺すこと
殺菌は文字通り「菌を殺すこと」を指します。細菌・ウイルス・微生物などが殺菌の対象です。ただし、対応できる菌の数や種類、程度には規定がありません。一部の菌だけでも殺せれば殺菌と表記されます。
消毒
消毒は微生物のなかで人体に有害なもの(病原性微生物、毒)を無毒化あるいは殺菌することを指します。消毒は殺菌のなかでも限定的な概念といえます。
滅菌
滅菌は殺菌によって、菌をほとんどゼロにすることを指します。「殺菌」と比べると、効果の程度が明確化されている用語です。
なお、医療・製薬の現場では、細菌・ウイルス・微生物の種類や有害性の有無を問わず、菌が生存する確率が100万分の1になった状態を「滅菌」と定義します。
除菌は菌を取り除くこと
除菌は菌の生死を問わず、対象物から取り除かれることを指す言葉です。たとえば、テーブルの上で繁殖している菌をアルコールを浸した紙で拭き取った場合、紙の上で菌が生存できたとしても、テーブルからは菌が取り除かれるため除菌といえます。
製品別の表記の違い
抗菌・静菌・殺菌・除菌の用語は使用できる製品が異なります。製品の種類ごとに詳しく解説します。
衣服・布製品は抗菌・制菌
衣服や布巾などの布製品では、「抗菌」または「制菌」と表記されます。繊維に抗菌剤を練り込んだり、生地表面を加工したものが対象です。
衣服に関して「抗菌」というときは一般的に、細菌に起因する臭いを抑えられることを指します。JIS規格(日本産業規格※)の基準に照らせば、細菌の増殖を100分の1以下に抑えられるレベルです。
一方、制菌は抗菌よりも対象とする菌の種類が多く、感染予防を目的としています。飲食店・サービス・医療現場の衣服に求められる機能です。制菌加工も抗菌剤を使用するため、試験方法は抗菌のJIS規格に基づきます。
なお、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証制度に合格した抗菌・制菌生地にはSEKマークが表示されます。対象とする菌がわかるので、商品選びの基準として有用です。SEKマークの詳細は「衣服の抗菌・制菌はSEKマークで見分ける」の項目で詳しく解説します。
(※)抗菌性(JIS L 1902:繊維)
家電製品は抗菌・除菌
家電製品では効能・効果試験を実施し、全国家庭電気製品公正取引協議会が定める表示ルール、業界団体の基準をクリアした製品に「抗菌」または「除菌」が表記されます。
全国家庭電気製品公正取引協議会の定義では、抗菌はJIS Z 2801(日本産業規格)に適う細菌のみを対象とした効果、除菌は物質または空間から微生物を除去することです。エアコンや空気清浄機、食器洗い乾燥機などが試験の対象となります。
JIS Z 2801の詳細は次のとおりです。
医薬品・医薬部外品は殺菌・消毒・滅菌
「殺菌」「消毒」「滅菌」は医薬品または医薬部外品以外では使えない言葉です。このことは「医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」で定められています。医薬品は治療を目的としたもの、医薬部外品は防止・衛生を目的としたものです。
消毒液やハンドソープなどが医薬部外品として該当します。ただし、医薬品は有効成分の効果が厚生労働省に認められたもの、医薬部外品は厚生労働省が許可した有効成分を一定濃度で配合したもののみです。メーカーが自由に表記することはできません。
一般的な洗剤・拭き取りシートは除菌
医薬品・医薬部外品に該当しない、一般的な洗剤や拭き取りシートでは「除菌」と表記されます。除菌の表記に関する法律はありませんが、清掃や洗浄を目的とした製品は公正取引委員会の定義と試験に準拠するのが通例です。
また、実際には除菌効果がない、あるいは実証できないにも関わらず「除菌」を標ぼうすると、景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)に抵触します。
各用語の違い一覧
ここまでのまとめは次の通りです。
(※)公正取引協議会「家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約」
衣服の抗菌・制菌はSEKマークで見分ける
一般社団法人繊維評価技術評議会 JEC301 SEKマーク繊維製品認証基準(2025年4月1日改定版)
衣服や清掃クロスなどの布製品では、SEKマークが抗菌・制菌効果のある製品選びの基準となります。
SEKマークとは
SEKマークは一般社団法人繊維評価技術協議会が定める、製品認証制度をクリアした製品で表示できるマークです。「S:清潔」「E:衛生」「K:快適」を意味しています。製品認証は第三者試験機関による試験と第三者委員会の評価の結果に基づく客観的なものです。
機能・用途ごとにSEKマークがあり、ひとつの製品で複数のSKEマークの認証を受けているものもあります。
SEK青・SEK橙・SEK赤が抗菌・制菌
※◎が必須、〇が任意
抗菌・制菌が該当するのはSEK青・SEK橙・SEK赤の3種類です。それぞれを詳しく解説します
DIC66(青):抗菌防臭加工
青の十字で示したSEKマークは抗菌防臭効果があることを示しています。抗菌効果の試験で対象となる菌は黄色ブドウ球菌です。抗菌防臭効果が基準を満たしており、衣類の場合は10回洗濯しても劣化しないことが認められた場合に、SEK(青)マークを表示できます。
なお、黄色ブドウ球菌の有害性は後述の「抗菌加工と制菌加工が抑制する菌の違い」で詳しく解説します。
DIC121(橙):制菌加工
オレンジ(橙)の十字で示したSEKマークは、一般家庭・飲食・サービス業などの一般用途向けの制菌効果があることを示しています。
制菌の対象となる菌は黄色ブドウ球菌と肺炎かん菌です。また、必須ではありませんが緑膿菌・大腸菌・モラクセラ菌は任意で試験の対象にしています。試験における洗濯回数は10回が基本で、業務用の場合は50回の洗濯が行われる場合があります。
DIC156(赤):制菌加工
赤の十字で示したSEKマークは、医療機関・介護施設向けの制菌効果があることを示しています。黄色ブドウ球菌・肺炎かん菌・MRSAの抑制が必須項目であり、緑膿菌・大腸菌・モラクセラ菌が任意です。
また、SEK(青)・(橙)の試験における洗濯回数が10回であるのに対し、SEK(赤)は50回の洗濯でも劣化しないことが認められる必要があります。
抗菌防臭加工と制菌加工が抑制する菌の違い
SEKマークの基準に則ると、抗菌防臭加工と制菌加工では抑制できる菌の種類に違いがあります。あらためて次の表をご覧ください。
ここでは、菌の種類ごとの特徴を詳しく解説します。
抗菌防臭加工が抑制する菌の種類
抗菌防臭加工で抑制できる菌は黄色ブドウ球菌です。黄色ブドウ球菌は人の手指や喉・鼻の中、皮膚などに常在する菌で、健康な人の40%が保有するとされています。黄色ブドウ球菌が常在していても、健康であれば免疫で対処できるため症状は現れません。
しかし、汚染された食品や咳・くしゃみの飛沫などによって体内に侵入すると、吐き気や嘔吐、腹痛などの食中毒症状が現れます。免疫が下がっているときは皮膚感染の可能性もあり、にきびや水虫、傷口の化膿になることもあります。
黄色ブドウ球菌のもうひとつの影響は悪臭です。黄色ブドウ球菌が汗や皮脂をエサとして分解すると、汗臭と呼ばれる独特の臭いを放ちます。抗菌防臭加工の効果は、黄色ブドウ球菌の増殖を抑えることで悪臭を防止する効果です。
制菌加工が抑制する菌の種類
制菌加工では抗菌防臭加工よりも多い種類の菌の増殖を抑制します。一般用途・医療介護用途の必須項目で共通しているのは、黄色ブドウ球菌と肺炎かん菌です。
肺炎かん菌は人の口腔や腸管に常在していますが、免疫が低下していると肺炎・尿路感染症・敗血症などを引き起こします。
医療介護用途では、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)も必須項目です。これも健康な人にとっては無害ですが、傷口に感染すると化膿をはじめとしてさまざまな症状をもたらします。通常の抗生剤(抗生物質)が利きにくく、院内感染につながる菌です。
なお、緑膿菌・大腸菌・モラクセラ菌は任意の項目であるため、製品によっては対応していません。
抗菌・制菌機能付きのユニフォーム
最後に、業界別の抗菌防臭・制菌加工ユニフォームを紹介します。
医療・介護
スクラブ
白衣
介護用エプロン
飲食・サービス
コックコート・調理用白衣
エプロン
シャツ
抗菌・制菌の違いを知って使い分けよう
抗菌と制菌では対象とする菌の種類や試験方法が異なることがわかりました。また、類似の単語である静菌・殺菌・消毒・滅菌・除菌とは対象となる製品の種類や、菌に対する効果に違いがあります。
衣類の場合はSEKマークが表示されているものを選びましょう。SEKマークがあれば、抗菌加工は黄色ブドウ球菌の抑制効果があること、制菌加工は黄色ブドウ球菌や肺炎かん菌など複数種類の菌を抑制することが認められています。
医療・介護・飲食・サービスなどの業界やシーンによって求められる抗菌・制菌レベルは異なるため、ぜひ違いを知って商品選びにお役立てください。
- 春夏向け作業着
- 空調服®・ファン付き作業着
- 作業着アウター・ジャケット
- 春夏向け長袖作業着シャツ
- 半袖作業着シャツ・七分袖シャツ
- 春夏向けコンプレッションウェア
- つなぎ
- スモック
- 春夏向けカーゴパンツ
- 作業着ショートパンツ・ハーフパンツ
- 春夏向けワークパンツ
- 秋冬向け・通年作業着・防寒着
- 防寒コート
- レインウェア
- 秋冬向けブルゾン
- 秋冬向けジャンパー
- 作業着スウェット・パーカー
- カーゴパンツ
- ワークパンツ
- アンダーウェア
- ワークエプロン
- 安全靴
- 長靴
- ヘルメット
- 秋冬向けアウター
- 秋冬向けポロシャツ
- 長袖作業着シャツ
- インソール
- 作業帽
- 防寒ベスト